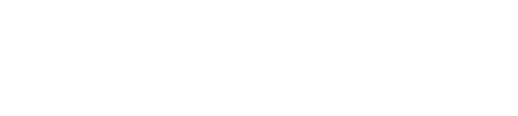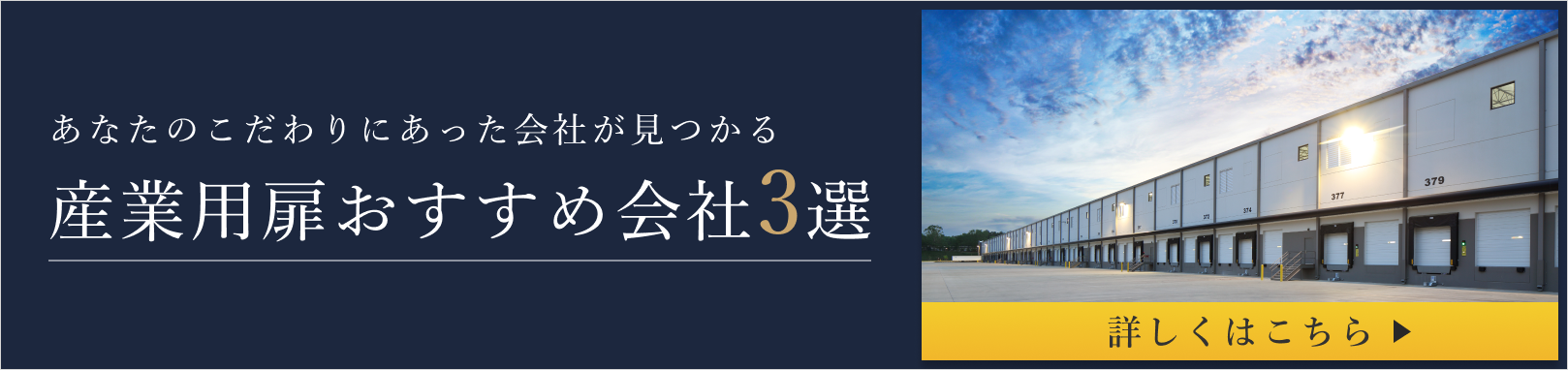「軽量シャッターを設置したい!」
「軽量シャッターの制作はどこに依頼すればいいの?」
お店だけでなく個人住宅の窓やガレージにも、防犯目的で設置されることの多い『軽量シャッター』。
シャッターと聞いてまず思い浮かべるのが、この軽量シャッターではないでしょうか。
防犯対策や雨風から家や車を守るために、軽量シャッターの設置を検討している方も多いことでしょう。
しかし、軽量シャッターにも様々な種類があるため、どうやって選べばいいか悩んでいる方もいるはず。
そこで今回は、軽量シャッターの選び方からおすすめ製作会社について解説します。
軽量シャッターを設置する際の参考にしてください。
また、以下の記事では産業用扉導入の際におすすめのメーカーを紹介していますので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。
軽量シャッターとは
軽量シャッターとは、一般的にスラットの厚さを薄くして軽量化されたモノを指します。
防犯性と機能性の高さによって、お店だけでなく個人住宅の窓やガレージにも設置可能です。
ただし、防火対策としての機能はないため注意してください。
軽量シャッターは下記2つに分けられます。
- 手動
- 電動
上記2つの特徴について、それぞれ解説していきます。
手動
手動シャッターは、手で上げ下げして開閉するシャッターです。
取付作業が比較的簡単で1日で終わるケースが多く、費用も他のシャッターと比べて抑えられることから、自宅の窓・車庫など個人用として使用されることが多くなっています。
ただし、開閉には人の力を要することから手間がかかり、特に悪天候だと開閉時の負担が大きくなるでしょう。
また、長年使っていると経年劣化や錆びが発生してしまい、重くなってしまうこともあるため、メンテナンスが必要となります。
電動
電動シャッターは、人の手を使わずに電力で開閉するシャッターです。
主に住宅・マンションの駐車場や倉庫の間口などで、使用されることが多くなっています。
シャッターの上げ下げがリモコン操作のため、開閉時には労力を必要とせず、雨の日でも遠隔操作できるため容易に開閉できます。
また、挟まれ防止のための安全装置がついてるため事故も少ないです。
ただし、手動シャッターと違って機械を使うため費用が高く、設置時も場合によっては資格をもってる業者に頼まなくてはなりません。
加えて、機械が故障するリスクもあるため修理コストがかかり、寿命は使う頻度にもよりますが10年から15年と言われています。
そのため、設置コストとメンテナンスコストを考えて検討するといいでしょう。
軽量シャッターの種類と用途
軽量シャッターは使用場所や目的によって最適な種類が異なります。
主な種類と適した用途を解説します。
住宅用軽量シャッター
住宅用軽量シャッターは、一般家庭の窓や勝手口、ガレージなどに設置されるタイプです。デザイン性に優れ、住宅の外観に調和するよう設計されています。また、防犯性と同時に、プライバシー保護や日よけ、防風・防塵といった機能も備えています。
近年は住宅のセキュリティ意識の高まりから、リモコン操作が可能な電動タイプや、センサーと連動して異常を検知すると自動的に閉まるスマートタイプも人気があります。特に戸建て住宅の1階窓部分への設置が増加しています。
店舗用軽量シャッター
店舗用軽量シャッターは、小売店や飲食店などの商業施設のファサードに使用されるタイプです。開閉頻度が高いため、耐久性に優れた素材が使用されています。また、防犯性と同時に店舗の印象を左右する重要な要素であるため、デザイン性にも配慮されています。
半透明のパンチングタイプを選ぶことで、閉店後も店内のディスプレイを外から見せることができ、営業時間外でも宣伝効果を発揮できます。多くの店舗では電動タイプが採用され、開閉時の手間を軽減しています。
倉庫・工場用軽量シャッター
倉庫や工場用の軽量シャッターは、比較的大きな開口部に設置され、作業効率や物流の流れを妨げないよう、高速開閉が可能なタイプが多く選ばれています。耐久性が重視され、頻繁な開閉に耐える仕様となっています。
特に物流施設では、フォークリフトや台車の出入りがスムーズになるよう、床面との段差が少ない設計が重要です。また、作業環境を考慮して防音・断熱性能を備えたタイプも選ばれています。
駐車場・ガレージ用軽量シャッター
集合住宅や商業施設の駐車場入口に設置されるタイプで、車両の出入りをスムーズにするとともに、防犯面での役割も担っています。リモコンやカードキーと連動したセキュリティシステムが組み込まれていることも多く、許可された車両のみが出入りできるようになっています。
大型の開口部に対応できる強度と、頻繁な開閉に耐える耐久性が求められます。最近では車両感知センサーやループコイルと連動して自動開閉する高機能タイプも増えています。
軽量シャッターの選定には、設置場所の特性や使用頻度、求める機能性(防犯、防風、断熱など)を考慮することが重要です。また、周辺環境との調和や将来的なメンテナンス性も選択の重要な判断基準となります。
軽量シャッターを選ぶポイント
ここからは、軽量シャッターを選ぶポイントとして下記3つを解説します。
- 操作方法
- 開閉方式
- 材質
シャッターの使用目的に応じて、自分に合った軽量シャッターを選びましょう。
操作方法
軽量シャッターの操作方法には、先ほど解説したように手動と電動の2種類があります。
手動シャッターは、開閉するのに手間がかかりますが、費用は電動よりも安く済むため導入しやすい点がメリットです。また、作りが電動よりもシンプルなため、故障のリスクも低くなるでしょう。
ただし、シャッターの開閉にはパワーが要り、力が弱い人の場合は負担が大きく、悪天候時の開閉は不便となります。
一方、電動シャッターは、リモコンを使って誰でも簡単に開閉でき、力や手間もかかりません。また、自動ロックをはじめとした、安全機能付きのシャッターであれば事故の予防も可能です。
しかし、電動シャッターは価格が高く、電動部分の故障リスクも高くなります。上記のことから、それぞれのメリット・デメリットを考えながら、総合的に判断するといいでしょう。
電動シャッターの最新トレンドとしては、スマートホーム連携機能が注目されています。スマートフォンのアプリから操作できるだけでなく、音声アシスタント(Amazon AlexaやGoogle Assistantなど)と連携して音声指示で開閉できる製品も登場しています。外出先からシャッターの状態確認や遠隔操作ができるリモート機能は、特に不在時の安全管理に役立ちます。
また、安全性の向上として、障害物感知センサーの精度が高まっており、小さな物体も検知して停止する機能や、挟まれた場合に自動的に反転する機能が標準装備されるようになっています。高齢者や小さなお子様がいる家庭では、これらの安全機能は特に重要な選択ポイントとなるでしょう。
開閉方式
重量シャッターの開閉方式は、大きく分けると上下式と横引き方式の2種類があります。
上下式はさらに、低価格で導入できる『巻き上げ方式』と、開閉スピードが速くて音も静かな『オーバースライダー方式』に分類することが可能です。
巻き上げ方式は低価格で導入できる分、つくりがシンプルで開閉音が大きめとなっています。オーバースライダー方式はスムーズに開閉できますが、設置するには天井部分の高さがなければ設置できません。
「天井に高さはないけれど、横側にスペースがある」という方は、シャッターを横へスライドさせて収納するタイプの横引き方式がおすすめです。
横引き方式は、手動でも開閉がしやすく、コストパフォーマンスも高いため安価で導入できます。シャッターを導入するスペースや予算を踏まえて、自分に合った開閉方式を選びましょう。
近年の軽量シャッターでは、開閉方式の進化により操作性が大幅に向上しています。特に注目すべきは、高速開閉タイプのシャッターです。従来の3倍以上のスピードで開閉できるモデルも登場しており、雨の日の出入りや防犯面で大きなメリットがあります。
また、静音設計の進化も見逃せないポイントです。特に住宅密集地域では、早朝や夜間の開閉音が近隣トラブルの原因になることもありますが、ベルトドライブ方式やモーターの改良により、従来品より最大70%も静かな製品も登場しています。生活音に敏感な住宅環境では、この静音性は重要な選択基準となるでしょう。
材質
シャッターの材質は、耐用年数や手入れの必要性などに影響するため、シャッター選びの重要なポイントです。
軽量シャッターの材質には、ステンレス製やスチール製・アルミ製など様々あります。
ステンレス製は錆や腐食に強く、品質面では最も優れている素材といえますが、費用が高くなりやすい点がデメリットです。
スチール製は、ステンレス製と比べると費用を半分程度に抑えられますが、錆や腐食に弱い傾向にあります。
アルミ製は錆や腐食に強く、価格はステンレス製とスチール製の中間となっているため、迷ったらアルミ製を選ぶといいでしょう。
上記のようにシャッターの材質は、費用や耐久面のバランスを見て自分に合ったモノを選んでください。
軽量シャッターのメンテナンスと寿命
軽量シャッターを長く安全に使用するためには、適切なメンテナンスが不可欠です。定期的なケアと点検によって、シャッターの寿命を延ばし、突然の故障を防ぐことができます。
定期メンテナンスの重要性
軽量シャッターは日常的に使用する機会が多いため、気づかないうちに摩耗や劣化が進行していることがあります。定期的なメンテナンスは、小さな問題を早期に発見し、大きなトラブルや高額な修理費用を未然に防ぐために重要です。
特に電動シャッターの場合、モーター部分や制御機構など、目に見えない部分の点検も必要です。多くのメーカーでは、年に1〜2回の定期点検を推奨しています。DIYでのメンテナンスも可能な部分もありますが、専門業者による点検を定期的に受けることで、安全性と機能性を長期間維持できます。
主なメンテナンス項目
軽量シャッターの主なメンテナンス項目には以下のようなものがあります:
- レール部分の清掃と潤滑剤の塗布
- スラット(シャッターの板部分)の清掃と点検
- スプリングの張力調整(手動タイプの場合)
- モーターと制御機構の点検(電動タイプの場合)
- 安全装置の動作確認
- 錆や腐食の有無のチェックと対処
特に海岸沿いや工業地帯など、環境が厳しい場所では、塩分や大気汚染物質による腐食が進みやすいため、より頻繁な点検と適切な防錆処理が必要です。
シャッターの平均寿命と延命策
軽量シャッターの平均寿命は、使用環境や頻度、メンテナンス状況によって大きく異なりますが、一般的には以下のように考えられています:
- 手動シャッター:15〜20年
- 電動シャッター:10〜15年(モーター部分は7〜10年)
ただし、適切なメンテナンスを行うことで、この寿命を大幅に延ばすことが可能です。特に以下の点に注意することで、シャッターの寿命を延ばす効果が期待できます:
- 定期的な清掃と潤滑剤の適用
- 適切な使用方法(乱暴な操作を避ける)
- 早期の部品交換(摩耗や劣化が見られたら迅速に対応)
- 環境に応じた防錆・防腐処理
- 専門業者による定期点検
多くの製造会社では、定期メンテナンスプランを提供しています。初期投資はかかりますが、長期的に見れば突発的な故障による高額修理や早期の全体交換を避けられるため、コスト面でもメリットがあります。
シャッターのトラブルは安全面にも直結するため、異音や動作の不具合を感じたら、早めに専門業者に相談することをお勧めします。特に電動シャッターの場合、安全装置が正常に機能しないと重大な事故につながる可能性もあるため、注意が必要です。
軽量シャッターのおすすめ製造会社
ここからは、軽量シャッターのおすすめ製造会社として下記3社を紹介します。
- 三和鋼業
- 三和シヤッター工業
- 金剛産業
それぞれ、実績が豊富で魅力的な製造会社となっています。
三和鋼業

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | 三和鋼業株式会社 |
| 住所 | 兵庫県尼崎市久々知西町2-39-2 |
| 電話番号 | 06-6429-8456 |
| 公式サイト | https://sanwa-door.jp/ |
三和鋼業は、1970年に大型扉・特殊扉の専門メーカーとして設立した会社です。
これまでに培われてきた高い技術力により、他社では取り扱いできない専門性の高い大型扉から、工場・倉庫・美術館などを含む商業施設の特殊扉製造を幅広く取り扱っています。
創業以来、フルオーダーメイドでのモノづくりにこだわってきたからこそ、一つとして同じ製品はありません。
三和鋼業でなら、あなたの使用目的を踏まえてあなたにぴったりの製品を届けてくれるでしょう。
また、過去には建築家『安藤忠雄氏』が手掛けるカーテンウォールの部材製造にも携わるほど、デザイン性や機能性に優れた製品を作る技術も有しています。
三和鋼業の特徴や施工事例について詳しく知りたい方は、下記の記事も合わせてご覧ください。
なお、以下の記事では三和鋼業について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
三和鋼業の軽量シャッター製品は、特にカスタマイズ性の高さと高度な技術力で知られています。標準的な製品では対応できない特殊な形状や用途に対して、オーダーメイドで最適な解決策を提供できる点が大きな強みです。特に、既存建物の改修や特殊な開口部への後付け設置など、難易度の高い案件に強みを持っています。
同社の製品は、一般的な軽量シャッターの基準を超える耐久性と安全性を備えていることがよく知られています。特に風圧に対する強度設計は業界トップクラスで、台風の多い地域での実績も豊富です。また、安藤忠雄氏との協業実績が示すように、デザイン性と機能性を高いレベルで両立させる技術力も評価されています。
アフターサービス面でも、フルオーダー製品を長期にわたってサポートする体制が整っており、製品導入後も安心して使用できる点が顧客から高く評価されています。部品の供給期間も長く、10年以上経過した製品でも適切なメンテナンスと修理が可能な場合が多いです。
三和シヤッター工業

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | 三和シヤッター工業株式会社 |
| 住所 | 東京都板橋区新河岸2-3-5 |
| 電話番号 | 03-5998-9111 |
| 公式サイト | https://www.sanwa-ss.co.jp/ |
三和シヤッター工業は、シャッター・ドアをはじめとする建築用製品の販売・施工や修理・点検などを行う総合建材メーカーです。
『安全・安心・快適』をスローガンに、都市空間や商空間・住空間のさまざまなシーンで、ユーザーの笑顔や幸せを守る製品を手掛けています。
そのため、緊急修理やメンテナンスに迅速に対応できるよう、24時間・365日・年中無休のフルタイムサービス体制を業界に先駆けて導入しました。
上記のような企業努力が実を結び、シャッター・スチールドアの国内シェア率がトップクラスをほこります。
三和シヤッター工業でなら、安心して活用できる性能の高いシャッターが手に入るでしょう。
三和シヤッター工業の特徴や施工事例について詳しく知りたい方は、下記の記事も合わせてご覧ください。

金剛産業

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | 金剛産業株式会社 |
| 住所 | 東京都中央区晴海1-8-12 |
| 電話番号 | 03-3534-1800 |
| 公式サイト | https://www.kongo.net/ |
金剛産業は昭和35年に設立して以来、産業用オーバードアー・住宅ガレージ・大型扉・特殊扉などを扱っている会社です。
よりユーザーに適した製品を提供するために、営業からメンテナンスまで責任を持って仕事を完結させる一貫体制を構築しています。
営業担当はユーザーの要望を的確に把握し、開発・設計担当は安全で優れた製品の図面を描き、製造・施工担当は熟練の技を駆使して製品を作り上げてくれるでしょう。
また、製品納入後はユーザーの立場に立った、きめ細やかなサポートも実施しています。
上記のように一貫体制の整っている金剛産業でなら、安心して任せられるでしょう。
金剛産業の特徴や施工事例について詳しく知りたい方は、下記の記事も合わせてご覧ください。

まとめ
今回は、軽量シャッターの選び方からおすすめ製作会社について解説しました。
軽量シャッターとは、一般的にスラットの厚さを薄くして軽量化されたモノを指します。
防犯性と機能性の高さによって、お店だけでなく個人住宅の窓やガレージにも設置可能です。
軽量シャッターを選ぶポイントは下記の3つとなります。
- 操作方法
- 開閉方式
- 材質
機能や耐久性によって費用も大きく異なるため、使用目的や予算・設置場所を踏まえて、自分に適したシャッターを選びましょう。
軽量シャッターを設置する際は、今回紹介した3社の中から依頼する会社を選ぶことをおすすめします。
3社とも実績と技術力に定評があるため、きっとあなたに適した軽量シャッターが見つかるでしょう。