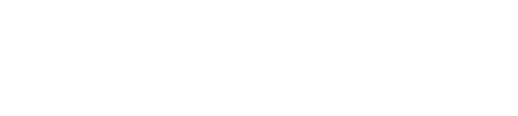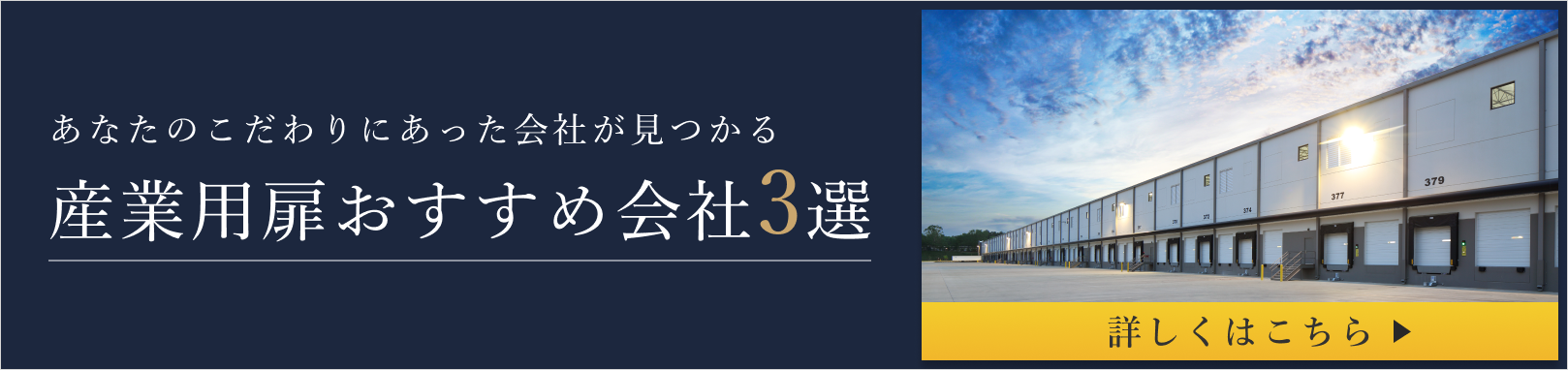「ヘリ格納庫を設置したい!」
「ヘリ格納庫の選び方は?」
ヘリ格納庫を製造したい方の中には、何を基準に選べばいいのかで悩んでいる方もいることでしょう。ヘリの保管環境が悪いと、ヘリの性能を維持できず、メンテナンスや修理に高額な費用が発生してしまうこともあります。
そのため、ヘリを安全に整備・保管するためにも、性能の良いヘリ格納庫が必要不可欠です。とはいえ、ヘリ格納庫はさまざまあり、製造会社も複数あるため依頼するのにも困難でしょう。
そこで今回は、ヘリ格納庫の選び方からおすすめの製造会社を解説します。この記事を読めば、あなたに適したヘリ格納庫を見つけられるでしょう。
また、以下の記事では産業用扉導入の際におすすめのメーカーを紹介していますので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。
ヘリ格納庫の種類

ヘリ格納庫の種類は以下の3つです。
それぞれの特徴を把握して、適切な格納庫選びに活かしてみてください。
固定式
固定式のヘリ格納庫は、地上に恒久的に設置される構造物で、主に鉄骨やコンクリートなどの堅牢な素材で建設されます。耐久性と安全性に優れており、長期間にわたって安定した運用が可能です。
天候の影響を受けにくく、ヘリコプターの機体や関連設備を保護する役割を果たします。また、空調や整備設備を内部に設置することもでき、運用効率の向上にもつながります。
固定式は一度設置すると移動が困難であるため、設置場所の選定が重要です。空港や病院、官公庁の施設など、使用頻度が高く、長期的な利用が見込まれる場所に適しています。
初期投資や建設期間は必要となりますが、維持管理がしやすく、長期的なコストパフォーマンスに優れるのが特徴です。
可動式
可動式のヘリ格納庫は、必要に応じて移動や展開が可能な構造を持つのが大きな特徴です。固定型の格納庫とは異なり、使用環境や設置場所に柔軟に対応できるため、多様な運用に適しています。
金属製のフレームと耐候性の高いシート材で構成されていることが多く、軽量でありながら一定の耐久性を持ちます。必要なときに展開し、使用しないときは収納や移動が可能なため、スペースの有効活用にもつながるのがポイントです。
また、建築確認申請が不要な簡易型の可動式格納庫も存在し、設置の手間やコストを抑えられるのも利点です。ただし、恒久的な使用には不向きであり、風雪への耐性や法規制への配慮も求められます。
可動式格納庫は、機動性を重視する運用や臨時的な格納スペースの確保に適した選択肢です。
仮設型
仮設型のヘリ格納庫は、短期間の使用や移動を前提とした設計が特徴です。常設型と異なり、必要な場所に迅速に設置できるため、災害時の緊急対応や期間限定の運用に適しています。
主に軽量な金属や布素材で構成されており、構造もシンプルなため、組み立てや解体が比較的容易です。また、建築確認の手続きが簡略化される場合もあるため、時間とコストの両面で効率的です。
ただし、耐久性や気密性、耐風性といった面では常設型に劣ることがあり、長期的な運用には適していません。仮設型は用途や期間に応じて柔軟に対応できる点が強みですが、設置環境や使用目的を明確にした上で選定する必要があります。
ヘリ格納庫を選ぶポイント

はじめに、ヘリ格納庫を選ぶ下記3つのポイントを解説します。
上記を参考にして、自分に適したヘリ格納庫を選んでください。
ヘリのサイズ
ヘリ格納庫を選ぶ際は、使用するヘリのサイズを考慮して適切な広さを確保しましょう。ヘリの主回転直径や全長を正確に測定し、それに合わせた広さの格納庫を選ぶことで、ヘリを安全に保管できます。
例えば、主回転直径が10mのヘリを保管する場合、少なくても12m以上の幅が必要です。ヘリ格納庫が保管するヘリに対して狭ければ、ヘリの損傷や事故のリスクが高くなります。
そのため、安全かつ効果的にヘリを保管するためにも、ヘリのサイズに注意しましょう。
材質と耐久性
ヘリ格納庫には、大きく分けるとスチールとアルミニウムの2種類の材質があり、それぞれ特徴が異なります。スチール製は強度と耐久性に優れており、長期間の使用にも耐えられるのが特徴です。
しかし、錆びやすいという欠点があります。アルミニウム製は、軽量で耐食性に優れているため、メンテナンスの手間が少ないです。
一方、強度にはやや難点があり、設置環境には考慮する必要があるでしょう。上記のような特徴を踏まえて、自分に最適な材質を選んでください。
機能性
ヘリ格納庫を選ぶ際は、格納庫の機能性が重要です。ヘリ格納庫は屋外に設置するため、さまざまな地域や気候条件に対応する機能が求められます。
例えば、雨や雪からヘリを守るためにも防水性が求められるため、特殊な防水加工が施された素材や、隙間を完全にふさげる構造があると良いでしょう。
また、ヘリは温度や湿度の変化に敏感なため、格納庫の内部には適切な通気性が求められます。そのため、断熱材を使用していたり、換気システムが備わっている格納庫を選びましょう。
上記のような格納庫を選ぶことで、ヘリを安全に保管できます。
ヘリ格納庫の安全対策

ここからは、ヘリ格納庫の安全対策として下記3つを解説します。
上記は、人命やヘリの安全性を確保する上で重要なポイントとなるため、必ず抑えておきましょう。
防火対策
防火対策はヘリ格納庫の安全対策において最も重要なポイントの一つです。ヘリ格納庫はヘリの保管場所であり、万一の火災が発生するとヘリや人命が危険にさらされる可能性があります。
そのため、下記のような防火対策を実施しましょう。防火壁の設置 消火設備の整備 定期的な消防訓練の実施防火壁や消火設備を設置することで、火災が起きた際に火の広がりを防ぎ、迅速に鎮火できます。
また、定期的な消防訓練を実施することで、消防に関する知識や技術を維持し、火災が発生した際には迅速かつ正確に対応できるでしょう。
上記のような対策が適切に実施されることで、ヘリ格納庫内での火災リスクを最小限に抑え、ヘリの安全性と人命を確保できます。
温度・湿度の管理
ヘリ格納庫において、適切な温度・湿度の管理は航空機の安全性を保つために非常に重要です。高温や低温環境では、金属の膨張や収縮が起こり、部品の強度に影響を及ぼすことがあります。
そのため、ヘリ格納庫内の温度は空調システムや暖房装置・冷却装置を設置して、適切に調整しましょう。また、加湿器や除湿機を使用して格納庫内の湿度を適切に調整できれば、腐食や金属疲労を防ぐことが可能です。
上記のように、適切な温度・湿度管理が行われることで、ヘリの構造や部品の健全性を保ち、安全な運航を実現できます。
セキュリティ対策
安全なヘリ格納庫を維持するためには、セキュリティ対策が必要不可欠です。パスワードやカードキーなどの電子施錠によって、閉鎖された場所へのアクセスを制限すれば、不正な侵入者の入室を防げます。
また、ヘリ格納庫内に監視カメラやセンサーなどのセキュリティシステムを設置すれば、不審者や異常な動きを検知し、即座に対処することが可能です。
近年では、顔認証や指紋認証などのバイオメトリクスを活用した高度なセキュリティシステムも登場しているため、さらに安全性が増しています。
上記のようなセキュリティ対策をすることで、不正な侵入や盗難・破壊行為のリスクを最小限に抑えられるでしょう。
ヘリ格納庫を設置する際のポイント

ヘリ格納庫を設置する際のポイントは以下の3つです。
それぞれのポイントを把握して、格納庫選びで失敗しないようにしましょう。
大開口のサイズを広く取る
ヘリ格納庫を設置する際には、大開口のサイズを広く取ることが極めて重要です。ヘリコプターの出入りをスムーズにおこなうためには、十分な開口部を確保する必要があります。
開口が狭い場合、機体の進入や退出時に旋回や切り返しが必要で、時間や労力がかかるだけでなく、接触や事故のリスクも高まります。また、緊急時に迅速な出動が求められる運用では、大開口による効率的な出入りが大きなメリットになるでしょう。
格納庫の設計段階で必要なクリアランスを正確に見積もり、ヘリのサイズや運用方法に応じて余裕を持った寸法設定が不可欠です。さらに、開口部が広ければ、大型ヘリの格納や複数機の同時運用にも対応しやすく、将来的な運用拡張にも柔軟に対応できます。
空調システムを整える
格納庫内の温度や湿度を適切に管理すると、ヘリコプター本体や搭載機器の劣化を防ぎ、長期的な保守コストを抑えられます。特に、電子機器やバッテリー類は高温や結露に弱く、環境条件によって性能が低下する可能性が高いです。
外気の影響を最小限に抑え、一定の空調状態を保つ必要があります。また、空調システムには冷暖房だけでなく、換気や除湿の機能も求められます。
メンテナンス作業中の作業員の安全や快適性も考慮する必要があるでしょう。適切な空調設備を設計段階で導入することにより、機体の保護と作業効率の向上を同時に実現できます。
床面の体重性を考慮する
ヘリ格納庫を設置する際には、床面の耐重性を十分に考慮する必要があります。ヘリコプター本体に加えて、メンテナンス機器や燃料、部品などが床にかかるため、床面には相当な荷重がかかります。
床面がその荷重に耐えられなければ、沈下やひび割れが発生し、安全性や機能性に重大な支障をきたす可能性が高いです。特に離着陸時の振動や衝撃も加わるため、単純な静荷重だけでなく動荷重も想定した設計が必要です。
また、コンクリートの厚みや鉄筋の配置、地盤の支持力なども重要な要素といえるでしょう。地盤調査の結果を基に構造設計をおこなうことで、長期的な耐久性と安全性が確保されます。
ヘリ格納庫を依頼する業者の選び方

ヘリ格納庫を依頼する業者の選び方は以下の7つが挙げられます。
それぞれのポイントを把握して、適切な業者選びに活かしてみてください。
施工実績が豊富か
施工実績が多い業者はさまざまな敷地条件や設計要望に対応してきた経験があるため、技術的な引き出しが豊富です。また、過去の実績から設計・施工の精度や安全性、耐久性に関する信頼性も判断できます。
ヘリ格納庫は一般の建築物と異なり、航空機の特性に配慮した構造や設備が必要です。 施工実績が豊富な業者であれば、換気設備、防火対策、騒音対策といった専門的な要素にも的確に対応できます。
さらに、行政手続きや法令への理解も深く、スムーズなプロジェクト進行が期待できます。実績は単なる数ではなく、過去にどのような規模や用途の格納庫を手がけたか、内容を精査することが重要です。
開発からサポートまで一貫しているか
ヘリ格納庫の建設を業者に依頼する際は、開発からアフターサポートまで一貫した対応が可能かどうかを確認することが重要です。
プロジェクトの各段階で担当が分かれている場合、情報伝達のミスや責任の所在が不明確になり、工期の遅延や追加コストが発生するリスクが高まります。
設計から施工、設備の導入、さらには完成後の点検や保守まで、一社で対応できる体制が整っている業者であれば、意思疎通がスムーズに進み、品質管理も一元化されます。
また、特殊設備を伴うヘリ格納庫において、安全基準や法令への適合が求められるため、初期段階から運用まで見据えた技術的な提案が可能な業者の方が信頼性は高いです。
カスタマイズに対応しているか
業者がカスタマイズに対応しているかどうかを確認することも重要です。標準仕様のままでは、設置場所や保管する機体の大きさ、運用目的に適さない可能性があるためです。
たとえば、扉の開閉方式や耐風性能、内部設備の有無などは、運用効率や安全性に直結します。柔軟に対応できる業者であれば、利用者の要望に沿った最適な設計が可能です。
また、カスタマイズに対応している業者は、設計や施工に関する知識や実績が豊富であることが多く、施工後のメンテナンスやアフターサポートにも信頼性があります。結果として、初期費用だけでなく長期的な運用コストや利便性にも大きな差が生まれるのです。
ヘリ格納庫の依頼先を選定する際は、単に価格や納期を見るだけでなく、どれだけ柔軟な対応が可能かを重視しましょう。
信頼できる業者か
格納庫は航空機の保管という特殊な用途であり、高度な専門知識と施工実績が求められます。まず確認すべきは、該当業者が航空施設や格納庫に関する施工実績を持っているかどうかです。
実績が豊富な業者は、法規制や安全基準を理解しており、設計・施工の段階で適切な対応が可能です。次に、構造や素材に関する提案内容も判断材料となります。
耐風性・耐震性・防錆性など、格納庫特有の要求に対して技術的な説明ができる業者は信頼性が高いでしょう。さらに、アフターサポート体制の有無も重要です。
完成後の点検やメンテナンスへの対応が明確であれば、長期的な安全性が担保されます。業者の選定は、単なる価格比較ではなく、技術力・実績・対応力を総合的に評価することが大切です。
サポート体制が充実しているか
サポート体制が充実しているかどうかも確認しましょう。格納庫は建築物としての性能だけでなく、安全性や法令への適合性、将来的なメンテナンスにも関わるため、長期的な視点での支援が求められます。
設計段階での相談対応や行政手続きに関するサポートの有無、建築後の点検や修繕対応の体制が整っているかは、信頼できる業者を見極めるポイントです。また、トラブル発生時の対応速度や、専門知識を持ったスタッフの配置状況なども判断材料になります。
単に建物を建てるだけでなく、継続的な運用を見据えた支援があるかどうかを見極めることが大切です。ヘリ格納庫は特殊性の高い施設であり、万全なサポート体制が整っていない業者に依頼すると、後々の運用に支障をきたす恐れがあります。
複数社を比較する
ヘリ格納庫の建設を依頼する際は、複数の業者を比較検討することも重要です。一社の提案だけで決定すると、コストや性能、納期において不利になる可能性があります。
まず、設計・施工実績を確認し、ヘリ格納庫のような特殊構造物に対する知見と経験があるかを見極める必要があります。過去のプロジェクトやクライアントからの評価も判断材料です。
次に、見積内容の内訳を詳細に比較することが求められます。価格だけでなく、使用する材料や設備仕様、工期、保証内容などを項目ごとに精査し、適正な提案であるかも見極めましょう。
また、アフターサービスの有無や対応範囲も比較対象とすべきです。格納庫は長期間の使用が前提となるため、維持管理の体制が整っているかも重要なポイントです。
複数業者を比較することで、最適なパートナー選定が可能となり、長期的な視点でコストと品質のバランスを確保できます。
予算内に収まるか
ヘリ格納庫を建設する際、複数の業者から見積もりを取り、価格の内訳を比較検討しましょう。総額だけで判断せず、設計費や施工費、各種申請費用などの明細を確認する必要があります。
次に、予算に対する柔軟性やコスト調整の提案力もポイントです。信頼できる業者であれば、必要な機能を維持しつつ、素材の選定や工法の工夫で費用を抑える提案をしてくれます。
また、過去の施工事例や実績を確認し、同規模・同条件の案件でどの程度のコストがかかったかを把握することで、適正価格かどうかの判断材料が可能です。契約前には追加費用の有無や変更時の対応について明確に取り決めておくことで、予期せぬ出費を防げるでしょう。
ヘリ格納庫のおすすめ製造会社

ここからは、ヘリ格納庫のおすすめ製造会社として下記3社を紹介します。
それぞれの製造会社について、詳しく解説します。
三和鋼業

三和鋼業は、1970年に大型扉・特殊扉の専門メーカーとして設立した会社です。
これまでに培われてきた高い技術力により、他社では取り扱いできない専門性の高い大型扉から、格納庫・工場・美術館などを含む商業施設の特殊扉製造を幅広く取り扱っています。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | 三和鋼業株式会社 |
| 住所 | 兵庫県尼崎市久々知西町2-39-2 |
| 電話番号 | 06-6429-8456 |
| 公式サイト | https://sanwa-door.jp/ |
創業以来、フルオーダーメイドでのモノづくりにこだわってきたからこそ、一つとして同じ製品はありません。過去には建築家『安藤忠雄氏』が手掛けるカーテンウォールの部材製造にも携わるほど、デザイン性や機能性に優れた製品を作る技術も有しています。
三和鋼業でなら、あなたの使用目的を踏まえてあなたにぴったりの製品を届けてくれるでしょう。
なお、以下の記事では三和鋼業について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
金剛産業

金剛産業は昭和35年に設立して以来、産業用オーバードアー・住宅ガレージ・大型扉・特殊扉などを扱っている会社です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | 金剛産業株式会社 |
| 住所 | 東京都中央区晴海1-8-12 |
| 電話番号 | 03-3534-1800 |
| 公式サイト | https://www.kongo.net/ |
よりユーザーに適した製品を提供するために、営業からメンテナンスまで責任持って仕事を完結させる一貫体制を構築しています。
営業担当はユーザーの要望を的確に把握し、開発・設計担当は安全で優れた製品の図面を描き、製造・施工担当は熟練の技を駆使して製品を作り上げてくれるでしょう。また、製品納入後はユーザーの立場に立った、きめ細やかなサポートも実施しています。
上記のように一貫体制の整っている金剛産業でなら、安心して任せられるでしょう。
小俣シャッター工業

小俣シャッター工業は昭和20年に創業して以来、長い時間をかけてシャッターを中心とした各種防災製品の研究・開発・アフターサービスに注力してきた会社です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | 小俣シャッター工業株式会社 |
| 住所 | 東京都北区王子本町2-23-9 |
| 電話番号 | 03-3905-6211 |
| 公式サイト | https://www.omata-s.co.jp/ |
時代が変化していく中で、長年蓄積した独自ノウハウを製品にフィードバックし、ユーザーのニーズへ的確に対応しています。
小俣シャッター工業の確かな技術力と開発力は高い評価を得ており、海上自衛隊の護衛艦用シャッターや大型旅客機の格納庫用シャッターなど、様々な分野で既に多くの採用実績をほこるほどです。
現存する日本のシャッターメーカーの中で、もっとも歴史のある小俣シャッター工業だからこそ、他では真似できない独自性のある製品が手に入るでしょう。
まとめ
今回は、ヘリ格納庫の選び方からおすすめの製造会社を解説しました。ヘリ格納庫を選ぶポイントは下記のとおりです。
- ヘリのサイズ
- 材質と耐久性
- 機能性
ヘリ格納庫は、ヘリを安全に保管し、長期間運用していくためにも重要です。そのため、あなたのヘリに最適で性能の良い格納庫を選びましょう。
また、ヘリだけでなく人命の安全性を確保するためにも、今回解説したヘリ格納庫の安全対策も実際に取り入れてください。今回の記事を参考にしてもらえれば、ヘリを安全かつ長期的に保管できるでしょう。